本記事はプロモーションが含まれています
冷感日本四季平盃揃12点セット

17℃以下の冷たい飲み物を注ぐと、鮮やかな絵柄が浮かび上がる平盃(ひらはい)の12点セットです。
日本が誇る伝統工芸「美濃焼」の技術と、温度で色が変わる特殊なインクを融合させた、遊び心あふれる逸品。


春は桜、夏は花火、秋は紅葉、冬は雪景色…。 盃に広がる四季折々の風景は、まるで小さなアート作品のよう。見る人を魅了し、心にやすらぎを与えます。
お酒を嗜む時間を、より豊かに、特別なものへと変えてくれます。
高級感あふれる白松の木箱に収められたこのセットは、大切な人への贈り物や、海外の方へのお土産としても最適です。 驚きと感動を届ける、特別なひとときを演出します。


商品スペック
| 商品名 | 【平盃12点セット】冷感 日本伝統 | 美濃焼 |
| 素材 | 磁器 |
| サイズ | 直径9cm、高さ3.4cm |
| 重さ | 90g (1個あたり) |
| 容量 | 70ml |
| 生産地 | 岐阜県 |
注意事項
- 電子レンジ、食洗器、オーブン、直火、IHはご使用いただけません。
冷感日本四季平盃揃とは?美濃焼の特徴を解説
日本の伝統工芸品である美濃焼は、国内の陶磁器生産量の半分以上を占めています。今回は、そんな日本一の美濃焼がもたらす、冷感日本四季平盃揃とは?という疑問にお答えしながら、伝統技術と最新技術の融合による美濃焼の平盃の魅力に迫ります。
美濃焼は陶器か磁器か?といった基本的な特性から、美濃焼が安い理由は何ですか?という素朴な疑問、さらには磁器を電子レンジに入れるとどうなるか、美濃焼は食洗機で洗えるか、美濃焼は目止めは必要ですか?目止めをしないとどうなるかといった、お手入れに関するお悩みにもお答えしていきます。
美濃焼平盃を長く愛用するために知っておきたいこととして、美濃焼を初めて使うときはどうしたらいいか、美濃焼をより長く使うためのお手入れ方法、陶器と磁器それぞれの取り扱い注意点、目止めの手順と効果、知っておきたい土鍋や平盃のお手入れ方法、そして冷感日本四季平盃揃とは?その魅力と長く使うポイントまで、使ってる人の口コミ評判も交えて徹底的に解説します。
この記事を読むことで以下の疑問を解決できます。
- 美濃焼の基本的な特徴と冷感日本四季平盃揃の魅力
- 陶器と磁器の違いやそれぞれの取り扱い方
- 美濃焼を長く愛用するためのお手入れ方法
- 冷感日本四季平盃揃の正しい使い方と注意点
日本一の美濃焼がもたらす、冷感日本四季平盃揃とは?
- 伝統技術と最新技術の融合による美濃焼の平盃
- 美濃焼は陶器か磁器か?その特性を解説
- 美濃焼が安い理由は何ですか?
- 磁器を電子レンジに入れるとどうなる?
- 美濃焼は食洗機で洗えるか?
- 美濃焼は目止めは必要ですか?目止めをしないとどうなる?
伝統技術と最新技術の融合による美濃焼の平盃

美濃焼は、岐阜県東濃地方で1300年以上の歴史を持つ伝統的な陶磁器です。瀬戸焼、有田焼(伊万里焼)と並んで日本三大陶磁器の一つに数えられます。
冷感日本四季平盃揃は、この美濃焼の伝統に最新の技術を融合させて作られた酒器です。酒を注ぐことで、器の温度が下がり、絵柄が鮮やかに色づく仕組みを持っています。例えば、冷酒を注ぐと、桜、花火、紅葉、雪結晶の絵柄が浮かび上がり、日本の四季の美しさを楽しむことができます。
これらの絵柄は職人による手作業で丁寧に絵付けされており、17℃に近い温度で淡く色づき、冷たければ冷たいほどはっきりと発色します。加えて、ゆるやかに色が変わっていく様子とともに、お酒の色合いも映し出されるため、視覚的にも楽しむことができます。
飲み干せばゆっくりと元の色に戻るため、再びお酒を注いで変化を楽しむことができる点も特徴です。
美濃焼は陶器か磁器か?その特性を解説

美濃焼は、陶器と磁器の両方が生産されているため、一概にどちらとは言い切れません。陶器は粘土を主原料としており、粒子が粗く吸水性が高いという特性があります。そのため、温かみのある風合いが特徴です。
一方で、磁器はカオリンという石の粉を主原料とし、高温で焼成されるため、粒子が細かく吸水性がほとんどありません。つるりとした滑らかな質感が特徴で、陶器に比べて丈夫な作りになっています。
美濃焼は、この二つの性質を柔軟に取り入れ、時代に合わせて様々な器を生み出してきました。そのため、購入した美濃焼の製品がどちらの素材であるかを知るには、商品の説明を確認することが大切です。
また、器の底(高台)を見て、ザラザラしていれば陶器、つるりとしていれば磁器という見分け方もあります。
美濃焼が安い理由は何ですか?

美濃焼が比較的安価に手に入れられる主な理由は、その生産量の多さにあります。国内で生産される陶磁器の50%以上が美濃焼であり、日本一の生産量を誇ります。大量生産が可能であるため、製造コストを抑えることができます。
また、美濃焼は新しい技術を積極的に取り入れてきた歴史があり、これにより効率的な生産体制を築いています。さらに、黄瀬戸、瀬戸黒、志野、織部といった伝統的な四様式を基本としながらも、様々な色や形、絵柄の器が生産されており、日常使いしやすい製品が豊富です。
これらの要因が組み合わさることで、美濃焼は丈夫でありながらも手頃な価格で広く流通しています。
磁器を電子レンジに入れるとどうなる?

磁器は電子レンジでの使用が比較的安全です。その理由は、磁器が水分をほとんど吸収しないため、加熱による急激な水分の膨張が起こりにくいからです。
しかし、注意すべき点もいくつかあります。まず、金彩や銀彩などの金属装飾が施されている磁器は、電子レンジのマイクロ波と反応して火花を散らす恐れがあります。これは器の破損だけでなく、電子レンジ自体の故障や火災の原因にもなりかねません。
また、長時間加熱しすぎると器が非常に熱くなるため、取り出す際にはやけどに注意が必要です。このように、磁器は電子レンジに対応している製品が多いものの、装飾の有無や取り扱いには気を配るべきです。
美濃焼は食洗機で洗えるか?

美濃焼を食洗機で洗うことができるかどうかは、その製品が陶器か磁器か、そしてどのような装飾が施されているかによって異なります。一般的に、吸水性が低く硬質な磁器は食洗機に対応している製品が多いです。
しかし、陶器の場合は吸水性が高いため、食洗機の高温と洗剤が染み込み、ひび割れやカビの原因になる可能性があります。
また、美濃焼の製品全体に共通する注意点として、金彩や銀彩、上絵付けが施された器は、食洗機の洗剤や強い水流で装飾が剥がれたり、変色したりする恐れがあります。したがって、大切な器や繊細な装飾のある器は手洗いを推奨します。購入時に「食洗機対応」の表示を確認することが最も確実な方法です。
美濃焼は目止めは必要ですか?目止めをしないとどうなる?

美濃焼の中でも、特に陶器製の製品には目止めが必要です。目止めとは、器の表面にある目に見えない微細な穴を米のとぎ汁や小麦粉のでんぷん質で塞ぐ作業を指します。
これを怠ると、料理の汁気や油分が器に染み込み、シミやカビ、臭いの原因となります。特に、色や匂いが強い料理を盛り付けた場合、次に使用した際に匂いが残ってしまうことがあります。
また、目止めをすることで、器のひび割れや破損を防ぎ、長持ちさせる効果も期待できます。一方、吸水性のない磁器には、この目止めの作業は必要ありません。
美濃焼平盃を長く愛用するために知っておきたいこと
- 美濃焼を初めて使うときはどうしたらいいですか?
- 美濃焼をより長く使うためのお手入れ方法
- 陶器と磁器それぞれの取り扱い注意点
- 目止めの手順と効果について
- 知っておきたい!土鍋や平盃のお手入れ方法
- 冷感日本四季平盃揃とは?その魅力と長く使うポイント
美濃焼を初めて使うときはどうしたらいいですか?

初めて使用する際には、素材が陶器か磁器かを確認することが大切です。陶器の場合、前述の通り目止めを行うことが推奨されています。
目止めの具体的な方法としては、器が完全に浸るくらいの米のとぎ汁を鍋に入れて火にかけ、沸騰したら弱火にして20〜30分煮沸します。その後、火を止めて器が冷めるまで放置し、水で洗い流して自然乾燥させれば完了です。
この一手間をかけることで、粘りのあるとぎ汁が器の隙間を埋めて、料理の染み込みを防ぐことができます。磁器の場合は、特別な処理は必要ありません。台所用洗剤で表面の汚れを洗い流してからお使いください。
美濃焼をより長く使うためのお手入れ方法

長く愛用するためには、使用後のお手入れも大切です。まず、使用後は汚れたまま長時間放置せず、すぐに洗うことがシミやカビの発生を防ぐ上で重要です。洗浄後は、水分をしっかりと拭き取り、完全に乾燥させてから収納してください。
特に、陶器は吸水性が高いため、乾燥が不十分だとカビが発生する原因となります。最後に熱湯にくぐらせると、より早く乾燥させることができます。
また、硬い金属たわしや研磨剤入りのスポンジの使用は避け、柔らかいスポンジで優しく洗うようにしましょう。
陶器と磁器それぞれの取り扱い注意点

陶器・磁器については、それぞれ特性が違うため、取り扱い方法が異なります。
陶器は急な温度変化に弱く、例えば冷蔵庫から出してすぐに熱いものを入れるとひび割れの原因になることがあります。
磁器は吸水性がなく丈夫ですが、金彩や銀彩などの装飾が施されている場合は、電子レンジや食洗機の使用で装飾が剥がれることがあります。
また、どちらの素材であっても、器の底面はテーブルに傷をつける可能性があるため、引きずらないように注意することが大切です。
目止めの手順と効果について

目止めの手順は、まず、陶器をきれいに水洗いし、鍋に入れます。次に、器が完全に浸るまで米のとぎ汁を注ぎます。とぎ汁がない場合は、水に小麦粉や片栗粉を大さじ1〜2杯溶かしたものでも代用できます。
その後、弱火にかけて沸騰させ、20分から30分程度煮沸します。火を止めた後、そのままの状態で冷めるまで放置してください。最後に、器を取り出して水洗いし、しっかりと乾燥させて完了です。
この作業を行うことで、器の多孔質な隙間がでんぷん質で埋められ、汚れや匂いが染み込みにくくなり、器を長持ちさせる効果も期待できます。
知っておきたい!土鍋や平盃のお手入れ方法

土鍋や平盃も、陶磁器の特性に応じたお手入れが大切です。使用後は、完全に冷めてから水で優しく洗い、十分に乾燥させてください。
冷感日本四季平盃揃のように、絵柄の部分に強い摩擦や直射日光を長時間当てることは、染料が剥がれたり色褪せたりする原因になるため避けるべきです。
冷感日本四季平盃揃とは?その魅力と長く使うポイント

冷感日本四季平盃揃は、美濃焼の伝統と、冷たさに反応して色が変わる最新技術が融合した酒器です。冷酒を注ぐと、桜、花火、紅葉、雪結晶の絵柄が浮かび上がり、目でも四季を感じられることが最大の魅力です。
ご自宅用はもちろん、ゴールドの化粧箱に入った豪華なセットは、プレゼントや海外の方へのお土産にも適しています。この平盃を長く愛用するためには、いくつかのポイントがあります。
- 絵柄を強く擦らないよう優しく洗うこと
- 金属たわしや研磨剤入りの洗剤は使用しないこと
- 電子レンジやオーブンでは使用しないこと
- 紫外線に弱い染料のため、直射日光に長時間当てないこと
- 使用前に一度絵柄の部分を冷やすと、発色がよりはっきりすること
- 陶器の特性上、手作業による個体差があること
- 一度目止めを行うことで、よりはっきり発色すること
- 飲み口が広いためお酒の香りが立ちやすいこと
- ゆるやかな角度がつけられているため、香りと味わいを一番感じやすいこと
- 伝統的な形でありながら、現代の暮らしに馴染むモダンなデザインであること
- 熱燗でも冷酒でも楽しめること
- 化粧箱入りでギフトにも最適なこと
- 一献でたっぷり約40mlの容量があること
- すりきり容量は70ccであること
- 陶器でありながら、電子レンジや食洗機に対応している製品もあること


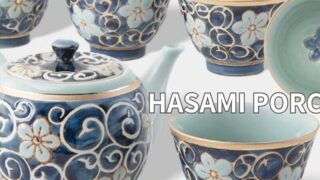








コメント